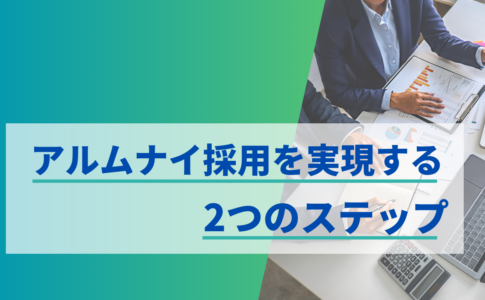この記事をお読みくださっているということは、人材獲得にお困りなのではないでしょうか?
年々、人材獲得競争は激化しており、2020年度版「小規模企業白書」によると、中規模かつ非製造業の企業のうち、85%の企業が「人材の確保・育成」といった人材に関連する課題が重要な経営課題のひとつであると答えています。
また、小規模企業や製造業でも人材に関する課題が重要であるとの回答は7割近くを占めており、業種や企業規模を問わず、人材獲得は企業の重要な課題となっていることがわかります。
今回の記事では、こういった多くの企業が人材獲得に課題を抱える中で、ライバル企業に差をつけられる採用手法を紹介します。
人材獲得が「競争」の対象となった背景
そもそもなぜ、こんなにも人材獲得が難しくなっているのでしょうか。これには、様々な要因がありますが、ここでは代表的なものを3つ紹介します。
少子高齢化による生産年齢人口の減少
日本では、他国でも類を見ないほどのスピードで少子高齢化が進んでいます。現在も毎年生産年齢人口は減っていますし、2060年の生産年齢人口は、5000万人を割ることが予測されています。こういった生産年齢人口の減少に伴って特に若年層の採用が激化しているのです。
労働力減少の対応策としては、定年退職後の再雇用や、定年を伸ばすなどの施策を実施する企業も増えています。しかし、これらの策は若年層に関する採用課題の解決にはなりません。
こういった背景から、企業はいかにして若年層を採用するかを考え様々な施策に取り組んでおり、それに伴い採用競争は激化の一途を辿っています。
企業に対する期待値の多様化
時代の多様化に伴って、求職者が企業に求めるものも変化・多様化しています。
例えば、1989年の新語・流行語大賞にランクインした「24時間戦えますか」という言葉があります。この言葉は、猛烈に働いてその分高い収入を得るのが良しとされたバブル時代を象徴しています。
対して現代は、「ワークライフバランス」が注目され、プライベートを充実させることに重きが置かれている時代です。しかし、そんな中でも「仕事を頑張りたい」「仕事に打ち込んで成長したい」といった希望を持つ人も今でもたくさんいます。
またこの他にも、給与よりもやりがいを求めたり、「どんな人と働くか」を重視する人もいます。このように働く人が企業に求めるものは、これまでのような画一的なものから、多様化しているのです。
そのため、これまでのように待遇や給与だけでは採用がうまく行かず、各社、社風や事業への想いなどをアピールする傾向が高まっており、人材獲得競争の激化に繋がっています。
転職率の増加に代表される人材の流動化
転職率は年々増加しており、特に24歳以下の転職率は前年比3倍と顕著な増加率をみせています。この年齢層では、上の世代に比べて転職への抵抗や不安感が少なく、転職が気軽かつ当たり前のものになってきています。
そしてこの世代が年齢を重ね、労働者人口の多数を占めるようになることで、人材の流動性が高まっていくことが予想されます。
つまり、企業は良い人材を採用し続ける必要があり、これが採用競争激化の要因となっているのです。
人材獲得競争を勝ち抜くコツとは?

こういった人材獲得競争がより一層激化していく時代の中でも、勝ち抜けるコツがあります。ぜひこれから紹介するコツを実践して、人材獲得競争を勝ち抜いていきましょう。
自社の魅力を明確にする
まずは、自社の魅力を明確化しましょう。
人材競争が激しく、競合他社もあの手この手を使って求職者に自社の魅力を伝えようとしています。その中で求職者を自社に惹きつけるためには、「弊社はこれが売りです!」と言えるような魅力を作ることが大切です。
選考時に応募者が他の企業を受けていることも多くあります。そういった状況でも、自社の魅力をはっきり定義できていれば、競合と比べてどういった点がいいのか応募者に的確に訴求できるでしょう。
その際、インパクトのある魅力がある必要はなく、例えば「弊社では退職後も企業とアルムナイが良好な関係を維持し、業務委託や再雇用が実際に発生しています」などといった退職後の関係をアピールするのも有効です。
>>アルムナイとは?人事・HR領域で注目される背景と大企業の導入事例
会社全体で取り組む
現在は、求人や会社公式HPの情報だけでなく、口コミサイトや社員のSNSでの生の声を重視して応募を決める求職者も多く、特に若い求職者ほどこの傾向が強いです。
このような時代には、例えば、採用部門だけではなく現場社員が採用に向けてSNSで投稿するなど会社全体で取り組みが非常に重要です。会社全体で取り組み社員の生の声を発信することで、ただ応募が増えるだけでなく、自社に合った人からの応募を獲得することができるのです。
多様な働き方を取り入れる
採用競争に勝つためには、働き方に柔軟性を持たせることも大切です。
例えば、週に何日かでもリモートワークに対応することで、遠方の求職者も応募しやすくなるかもしれません。
また、フレックス制度に代表される、毎日9時〜18時の8時間働くといった形ににこだわらず働ける環境を整備すれば、子育てや介護をしつつ働きたいという人も雇用しやすくなります。
こうした働く環境の柔軟性を高めることで、自社で働ける人の幅を広げるというのも、採用競争を勝ち抜くためには必要となってくるでしょう。
人材獲得競争の中で注目される採用メソッド3選

人材獲得競争の激化に伴って、採用手法も多様化しています。ここからは、人材獲得競争が激しい現代だからこそ注目されている採用メソッドを3つ紹介します。
アルムナイ採用
アルムナイとは、退職者を指す言葉。すなわちアルムナイ採用とは、退職者をもう一度採用すること、また採用しようとする試みのことを指します。
この手法を使って採用するには、退職者と良好な関係を築けていることや、退職者が自社に対してマイナスの感情を持っていないなどの条件が必要ですが、この条件さえクリアできるのであれば、育成コストや定着率の面から見てもメリットの多い採用手法です。
>>【人事トレンド】アルムナイ採用を導入するメリット・デメリット
アルムナイ採用で注意すべきなのは、良好な関係を築けていたとしても、退職したということは何か不満や働く上で問題があったということ。一人ひとりの退職者が何を理由に退職したのかを見極め、それぞれに合ったアプローチをしていく必要があるでしょう。
>>電通・クラレ・荏原製作所・中外製薬のアルムナイ制度導入に関する事例集
リファラル採用
リファラル採用は、社員からの紹介で採用していく手法です。(しばしば縁故採用と混同されることがありますが、違いは以下の記事で説明しています。)
>>縁故採用を禁止する企業が増えた理由 | デメリットと実態を調査してみた
この方法のメリットは、実際に働く社員の紹介であるためスキルやカルチャーのマッチ度が高いことです。選考の通過率も高い傾向にあり、効率の良い採用活動ができるでしょう。
ただ、選考に落ちた場合に紹介した側の社員が気を悪くしたり、次回以降の紹介のモチベーションが下がったりしないよう、ケアをする必要がありそうです。
>>リファラル採用とは?メリット・デメリットと採用時にありがちな注意点
SNS採用
最近、キャリアSNSのYOUTRUSTやLinkedInも盛り上がりを見せている注目のSNS採用。
キャリアSNSだけでなく、TwitterやInstagram、TikTokなどのSNSでも採用に繋がった事例は多く出てきています。
この記事を読んでくださっている方にも採用を目的としたSNSのアカウントを運用している方もいらっしゃるかもしれませんね。
SNS採用は、人となりが見えやすいことと、人と人との繋がりがベースになっているので関係構築をしやすいことがメリットです。
注意点としては、TwitterやInstagramのような匿名でも利用できるSNSの場合はSNSで謳っている実績と現実が乖離している可能性があることです。SNSの情報だけを信じず、選考でしっかり見極めることが必要になります。
また、自社でSNSを運用する際は、炎上防止策の徹底やもしも炎上した際の対応についてのルール整備を怠らないようにしましょう。
人材獲得競争にアルムナイ採用がおすすめな理由

これまでに紹介した採用手法の中でも、アルムナイ採用は特におすすめです。
定着率が高い
アルムナイは一度退職している分、自社の良い点だけでなく悪い点も理解しています。その上で、もう一度働きたいと考え入社しているため、入社後のギャップによる離職リスクは低く、定着率も高くなると考えられます。
育成コストが低い
以前自社で働いていた人であるため、退職以降の変わった点を教えるだけでよく、新規雇用者と比べて育成コストを抑えることができます。
ただ、以前居た人だから分かるだろうという姿勢になりがちな点は注意です。きちんと対話を重ね、何が分かって何が分からないのかを把握し、適切な育成を行いましょう。