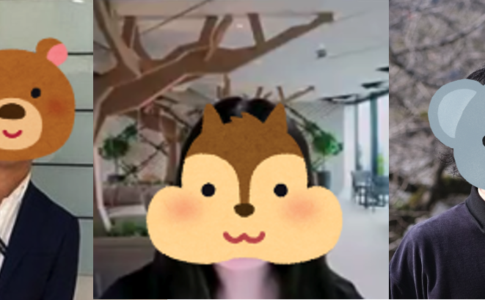数多ある事業ドメインの中から起業テーマを絞り、モック(試作品)を制作。
しかし、ようやく制作したモックを携えた資金調達では、投資家に断られる日々。
そして、頭をよぎる「資金ショート」
そんな従来の起業準備期間のリスクを解消する、新たな選択肢として、会社員として一定の給与を得ながら、起業家としても活動する「客員起業家(EIR)」を選択する起業家も現れてきています。
その1人が、京都大学イノベーションキャピタル(以下、京都iCAP)で、客員起業家(EIR)としてキャリアを歩み始めた松本凌氏。
自身が研究に関わったプロジェクトが、世界最大のテクノロジーの展示会「CES」に出展されるなど、前職・味の素では順調なキャリアを歩みながら、なぜ松本氏は客員起業家(EIR)という新しいキャリアパスを選択したのか?
松本氏のキャリアパスをたどりながら、「起業」でも「転職」でもない第3の選択肢──客員起業家(EIR)の魅力に迫ります。
世界初の電気調味料を開発し、CESに出展
松本氏は名古屋大学で修士課程を修了後、味の素へ入社。
味覚と嗅覚の研究開発に約9年間従事。
「うま味」を発見した味の素で、「第6の味覚を創り出すこと」が松本氏のミッションでした。
そして、大学の研究結果から「電気で人の味覚を調節したらどうか」というアイデアを思いつき、新概念となる調味料の可能性を提案。
味の素の社内起業家制度(イントレプレナー)として採択され、プロジェクトマネージャーとして「電気調味料」を世界で初めて開発されました。
この電気調味料プロジェクトは、世界最大のテクノロジーに関する展示会「CES」にて、味の素として初のハードウェア展示を実施。
社内起業家として挑戦しながら博士号も取得するなど、順調なキャリアを歩んでいました。
「野生の勘を取り戻したい」と「京都大学」看板の両取り
そんな順調なキャリアを歩んでいた松本氏は、なぜ味の素を退職する決断をしたのでしょうか?
「電気調味料のプロジェクトに区切りがついたら、より大きな挑戦をしてみたいと考えていました。大企業では得られない“野性の勘を取り戻したい”という思いや、ある種の“閉塞感”のようなものも感じていたのかもしれません」
起業を志すビジネスパーソンの中には、松本氏同様の閉塞感を感じている人も少なくない。同時に、大企業の看板や会社員としての安定を捨てられず、足踏みしているビジネスパーソンも少なくない。
松本氏は、どのようにしてそこから一歩踏み出すことができたのでしょうか。
京都iCAPのEIR制度では、会社員として一定の給与を得ながら、起業家としても活動できるため、新しい挑戦のセーフティネットになっています。
松本氏も「マイホームを購入してローンを背負った直後に、会社を辞めて起業の道に進むという大きな決断ができたのも、EIRのような仕組み・選択肢があったからこそだ」と語ります。
こうしたセーフティネットに加えて、松本氏が日々恩恵を感じているのが、京都大学の看板です。
「ピッチイベントや大学の先生との面談の際に非常に話が進めやすいと感じています。もし個人でアプローチをしていたら、連絡が返ってこないケースも多かったと思いますね。京都大学という巨人の肩に乗せてもらっている感覚です。」
そうした看板の力により、大手製薬会社の役員など、松本氏個人では繋がり得なかった立場の人物と繋がることができたことも「京都iCAPに所属しているからこそ得られた資産」と語っています。
EIRはモラトリアム期間
会社員と起業家のいいとこどり。
そんな特殊な職業でもあるEIRを、松本氏は「モラトリアム期間」と表現します。
「EIRは、ベンチャーキャピタルの支援を全力で受けながら起業家になれる仕組みです。大企業出身者がいきなり独立してディープテックスタートアップのファウンダーになるのは、ヒヨコがサバンナに放たれるようなもの。右も左も分からずに、失敗してしまうリスクがどうしても高くなってしまいます。一方でEIRの場合は、ディープテックスタートアップの世界とは何かを知り、起業家としての準備を行うモラトリアム期間を得ることができると考えています。」
「特別なカリキュラムがあるわけではない」
会社員と起業家のいいとこどりで、魅力的に見えるEIRですが、あえて向いていない人物についても、松本氏に尋ねたところ「真っ暗なトンネルのなかで、ライトがつくまで走れない人物は向いていない」という返答が返ってきました。
「真っ暗なトンネルには、落とし穴や危険があるかもしれない。それでも『そういう世界なのだから走るしかない』のがスタートアップ。ライトがつくまで走れない人物は向いていないですね」と松本氏。
京都iCAPの現状について「京都iCAPのEIRになったからといって、何か特別なカリキュラムが組まれていたり、手取り足取り教えてくれるわけではありません。必要な情報は自ら取りに行き、必要な人に聞きに行く、自力でペダルを漕ぐ姿勢が求められます。」とも語っています。
米国では研究者が引く手あまた。EIRへの挑戦は今がチャンス
そうした厳しい側面を指摘しつつも、松本氏はEIRは今こそチャンスと語ります。
「ディープテック領域は政府からの支援も手厚くなってきており、素晴らしい研究者が多数存在している一方で、EIRのようなファウンダー人材が圧倒的に不足しています。これは絶好のチャンスで、今なら素晴らしい研究シーズを持つ先生たちが、創業者やパートナーを求めています」
日本よりもエコシステムが成熟しているアメリカでは、研究者側が引く手あまたになっていますが、日本も今後数年で同様の状況になると松本氏は予測しています。
「EIRというシステムは、今後数年で成熟するという感触を持っているので、興味があるなら、まさに今やってみるべきだと思います」
そして、ディープテックに関わることについて「人類未踏の世界を最前線で見られる特権」と、松本氏は表現します。
「『パンドラの箱』というギリシャ神話がありますが、あのパンドラの気持ちが分かるんですよね(笑)神話では、その箱を開けてしまうことであらゆる災厄が起こってしまうんですけど、それを上回る知的探求心が強く、人類未踏の世界を最前線で見られる特権に魅力を感じています」
また、EIRに少しでも興味があるビジネスパーソンとぜひ交流したいと松本氏は語ってくれました。
「EIRとして活躍する起業家が集まるイベントを、9月25日に東京で開催予定です。私が所属する京都大学関係者だけでなく、九州大学、東北大学関係者も集まるので、アカデミアの研究を活用した、ディープテック領域での起業に興味がある方と、お話しできると嬉しいです」