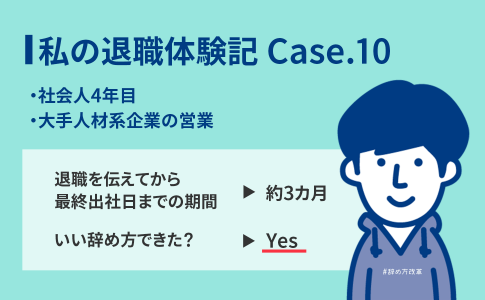さくら情報システム株式会社(以下、SIS)で同じプロジェクトを担当していた長野 千義さんと荻野 弘樹さん。配属や立場の違いを越えて、ともに数々の困難を乗り越えた元同僚同士です。
現在はそれぞれ異なる業界・企業で、社内SEやマネジメント、DX推進といった新たな領域に挑戦しながら活躍の場を広げています。そんなお二人に、SISで培った経験や、そこから踏み出した転職の決断、現在のキャリアに至るまでの道のりを伺いました。
過去、さくら情報システムに在籍していた方専用のネットワークです
技術と信頼で築いた、SIS時代の“土台”
——まずは現在のお仕事について教えてください。
長野:
現在は、半導体製造業の企業で、いわゆるDX推進部門を立ち上げて経営企画本部に所属しています。昨年までは情報システムグループのグループ長として、組織の立て直しに務めておりました。
荻野:
私は教育系の企業で、社内SEとして働いています。スクラムマスターをしながら、自らコードも書いており、チーム開発と運用の両面で、プロダクトに長く関わる働き方を続けています。
——お二人ともSIS出身とのことですが、当時の入社経緯を教えてください。
長野:
私はSISが4社目でした。当時勤めていたスタートアップ企業の経営状態が厳しくなったことを機に、より大規模なプロジェクトに携われる環境を求めて転職を決めました。SIS は金融系SIerとしての安定感を魅力に感じたことに加えて、旧さくら銀行出身の親族がいたことで、親近感や縁を感じ、入社を決めました。
荻野:
私は新卒採用でSISに入社しました。文系出身だった私は、IT領域は専門外でしたが 「ノルマに追われず、じっくりと手に職をつけたい」という思いを強くもっていたため、未経験者でも積極的に採用していたSISを選びました。また、IT業界の中でも特に金融系SIerには将来性を感じていたことも、大きな決め手でした。
——実際に入社してみて、ギャップはありませんでしたか?
長野:
当時の上司に「LinuxやRDBMSに不慣れな人が多い」という状況を聞かされたことですね。Windowsサーバーやパッケージを中心に扱うSISの業態は、それまでフルスクラッチ開発の経験が長かった私自身にとってはギャップでした。でもその分、色々なことを任せてもらえる風土があり、やりがいを感じる場面が多かったです。
荻野:
私も同じくギャップはあったように記憶しています。ITといえば「パソコンに向かってプログラミング」しているイメージでしたが、入社後は会計パッケージの導入プロジェクトに配属となり、担当フェーズが上流工程であったこと、高い会計知識も求められたことに驚きました。
実際に配属された現場では、プログラミングより要件を取り纏めていく折衝が多く、はじめはギャップを感じる事が多かったです。ただ、早くからこういった上流工程を経験したことで、以降のプログラミングにも活かせる観点が養われ、自身のキャリアに大きく影響したことは間違いありません。
「この経験は外でも通用するのか」——転職の決意と成長
——SISでの経験で印象に残っていることを教えてください。
長野:
膨大なアクセスを処理するサービスの運用保守プロジェクトで、日本を代表するIT企業のクライアントと直接やり取りできた経験はとても貴重でした。プロジェクトメンバーがお互いに情報をオープンに共有する文化があったのも非常に良かったです。一方で、初めて一緒に仕事をするメンバーばかりだったこともあり、コミュニケーションが上手く取れていないチームもありました。そんな状況を上司だった森さんから聞いて「それなら任せてほしい」と自ら申し出て、チームをお任せいただいたことが荻野さんとの出会いに繋がります。
荻野:
そのプロジェクトに私も参画していくことになるのですが、台風や地震などの災害が発生するとユーザーからのアクセスが急増するサービスだったので、数百台のバックエンドサーバーの保守を任された時は色々な意味で燃えました(笑)。自身が手掛けたものが世の中に出て、ユーザーの反応をリアルタイムに肌で感じることができ本当に刺激的な体験でした。
それからは遂行難度の高いプロジェクトに呼ばれる機会が増えていきました(笑)。プロジェクトに必要な要員としてご指名いただけることを嬉しく感じるとともに、自信にもつながったと思います。また、チーム統制やコミュニケーション、緊急対応を経験することで磨かれた判断力は、今のスクラム開発にも活きています。
長野:
私もアサインされたチームの体制を一新した経験は、現職のマネジメントで役立っています。当時はマネジメント経験が浅かったのにも関わらず、「全部任せる」と言ってくれた上司には感謝しかありません。あのときの信頼が、挑戦する勇気に繋がっていると思っています。
——その後、転職を決意された理由は?
荻野:
長野さんが転職され、チームリーダーの後任を引き継いでから、日に日に「プロダクトに長く関わりたい」と思うようになり、事業会社に絞って転職活動を始めました。特に、リリース後にもプロダクトを継続的に改善していく仕事に携わりたいと考えていました。
SIerは、どうしても受託開発案件が多くなりがちですが、納品したら終わりではなく、エンドtoエンドで「プロダクトを育てていくプロセス」にやりがいを見出したことが転職を決断した大きな理由です。
長野:
私はSISで得た経験が「どこまで通用するか」を試してみたかったからですね。また、家庭を持ったこともキャリアを見直す大きなきっかけとなりました。
SISや転職先となる楽天でアジャイル開発やマイクロサービスアーキテクチャといった手法や思想に触れてきたことは、現職のDX推進部門でテーマとしているビジネスプロセスリエンジニアリング活動において、「ビジネスアジリティの実現に必要な技術」であることを理解するのに非常に良い経験でした。
振り返ってわかるSISの魅力と、未来をつなぐネットワーク
——SISを出た今だからこそ感じる、良かった点や課題はありますか?
長野:
何より、SISにはいい人が多いんですよ。真面目で、落ち着いて仕事ができる人たちが多かったように感じます。ギスギスした雰囲気もなく、心理的安全性が高い職場だったのは本当にありがたかったです。
荻野:
本当にそう思います。加えて、PMやSEとしての基礎力を、知らず知らずのうちに身につけられていたことにも、あとから気づかされました。明文化されたマニュアルがあるわけではなかったですが、現場での立ち居振る舞いや、上司の背中から学ぶことが多かったですね。
長野:
若手でもしっかりチャンスを与えてもらえる風土があったからこそ、今につながる経験を積めたのだと思います。与えられたプロジェクトを着実に形にしていく力は、SIS時代に徹底して鍛えられました。一方で、ビジネスのスピード感や変化への柔軟性という点では、もう少し強化できた部分もあったかもしれません。アジャイル開発のような新しい考え方に、もっと早く触れる機会があればと感じる場面もありました。
——アルムナイネットワークには、どんな期待を持っていますか?
荻野:
現在はスクラムマスターをしていますが、社内の枠にとどまらず、他の企業の現場ではどうしているのか、という情報を得たいと思うことがよくあります。SIS出身の人たちと、技術やマネジメントの悩みを気軽に共有できる場があれば、とても心強いですね。
長野:
たとえばオフラインの交流会や、テーマ別の小さな勉強会などがあっても良いですよね。そこから「一緒に何かやってみようか」という話になるのも理想的です。オープンソースのような感覚で、知見を持ち寄り、刺激し合える関係になれたら素敵だなと感じています。
また、後輩世代の相談に乗るような仕組みもあれば嬉しいです。たとえば転職やキャリアに悩む若手に対して、同じSIS出身の少し先を行く先輩としてアドバイスできる環境。そういう支え合いが生まれると、コミュニティとしての価値がより高まる気がします。
——最後に、これから参加する方へのメッセージをお願いします。
荻野:
アルムナイネットワークは受け身だと参加する意義が薄いかもしれません。しかし、少しでも良いので自分から動いてみると、意外なつながりやヒントが見つかることもあります。迷っている方がいたら、まずは一歩踏み出してみてください。
長野:
SISアルムナイの方々が悩んだときや迷ったときに「まずここに聞いてみよう」と 思えるような場所になってほしいと思っています。同じ会社で働いていたという共通点だけで、自然と壁がなくなるんですよね。また、SISから巣立っていった皆さんが、それぞれの知見を持ち寄る「知の集合体」として、このネットワークが機能していけば良いなと思います。
過去、さくら情報システムに在籍していた方専用のネットワークです